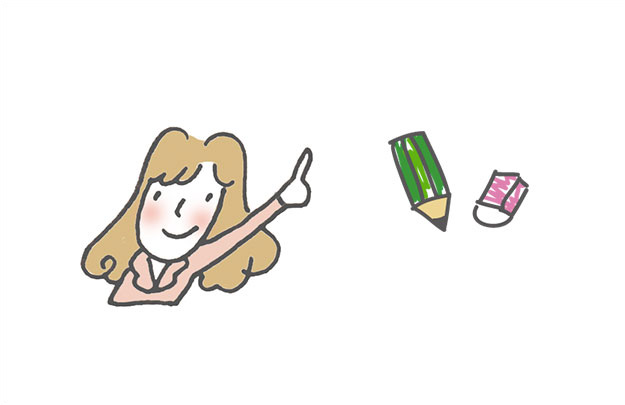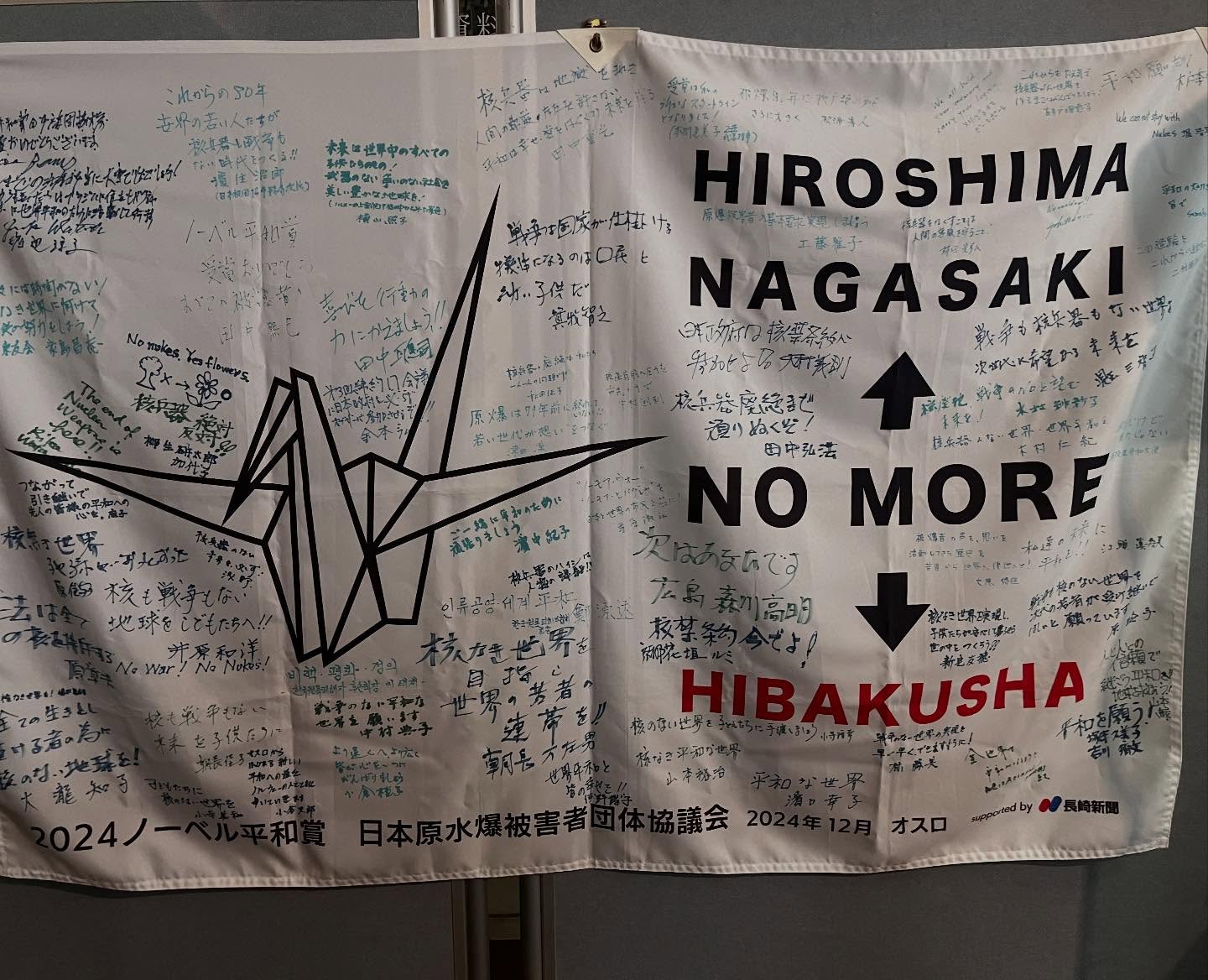2025年10月29日
令和6年度決算がおわりました!
令和6年度決算がおわりました!
討論原稿になります。
—
ただいまから、いたばし未来会議を代表し、「令和6年度東京都板橋区一般会計」及び4特別会計歳入歳出決算に賛成し討論を行います。
一般会計は、当初予算では2,530億円でしたが決算額は2699億円となり、最終的に169億円の増額となっています。
財政調整基金は当初、約50億円取り崩しましたが、最終的に109億円の積立を行い、残高は368億円にまで達しました。
近年、基金の増加が顕著です。財政調整基金はどこまで積み立ててもいいものか。何かあった際の備えが必要なことは理解するものの、基金の大幅な増加は、今を生きる人たちへの所得の再配分機能や公共サービスの充実が還元できていないともいえ、基準が必須です。
令和 6 年 2 月 15 日の基金及び起債の活用方針では、板橋区は、基金残高の目安は標準財政規模の概ね20~30%とするとしています。令和6年度の標準財政規模は、1569億円のため、計算すると、目安は314〜471億円となります。令和6年度の財政調整基金残高は368億円のため、すでに、目安に達していることになります。今後、7年度、8年度と同じように歳計剰余金を令和6年度と同じように財政調整基金に積み立てていくことは目安を大幅に超えていくため回避していく必要があります。
義務教育施設整備基金、公共施設等整備基金については、それぞれ25億円、22億円程度積み立てていけば、枯渇せず安定的な施設整備ができると令和6年2月に説明していましたが、今年度はそれぞれ約42億円、35億円と大幅に基金を積み立てました。想定よりも財源が余る、こういったことから、令和6年度は7回の補正予算を組み、対応してきたのかと思いますが、それでも尚、財源が余っている状況です。
こういう時にこそ、貧困の連鎖解消に向けた生活困窮支援や人材育成に財源を注ぐ必要があるのではないでしょうか。今後、財源を大幅に余らせることなく、未来への好循環への投資として、貧困支援やこどもたちのさまざまな経験ができる機会の提供や、興味を持った学習やスポーツ、文化活動等を続けられる学習クーポンによる支援や進学支援等にも力を入れていただきたいです。
また、障がい福祉や高齢者福祉においては、人材不足によるサービスの供給力不足や質の低下が今後ますます深刻になっていくと考えます。しっかりと人材育成、資格取得等、支援していくことで、当事者や働く人たちが生きがいを持てるようにお願いしたいと思います。
次に、個別の事業について申し述べます。
・LoGoフォームについて
令和6年度、電子申請システムLoGoフォームの推進が行われ、申請等がしやすくなったことは大変評価します。今後も、DXを推進し、よりよい行政サービスが提供されることを期待します。
・防災について
令和6年1月1日に能登半島地震がおき、区民の防災意識が高まっているタイミングで、防災カタログの事業が実施されたことは評価いたします。しかし、板橋区の感震ブレーカーをみんなに設置してもらいたいという気持ちには反し、設置があまり進まなかったのは課題です。
また、避難行動要支援者名簿については、水害地区だけでなく、全区で実施すること、地域と連携し、スピード感を持って進めていくことを要望いたします。
・非課税等高齢世帯エアコン購入費助成事業について
令和6年度東京都板橋区一般会計補正予算(第3号) で、エアコン購入費助成事業が行われましたが、これについては事業スキームが大問題でした。
1点目の問題点は、対象世帯は65歳以上で非課税世帯としており、絞り込み過ぎたことです。予算は6479万円で、当初は400世帯を想定していましたが、実際には、決算額は2983万円で助成件数は49件で12%の達成率となりました。生活保護世帯や本人非課税も支援の対象にするなど、工夫はできたと思います。また、高齢世帯に限る必要もなく、「家に1台もエアコンがついていない方を対象」という絞り込みも可能であったのではないでしょうか。2点目の問題点は、10万円のエアコンを助成するための事務費が、1件あたり51万円であることです。1件50万円をこえる事務費って、なんでしょうか。この事務費のかけ方は大問題ではす。エアコンの助成金額は49件の申請であったため、470万円が支出され、こちらは妥当です。しかし、49件470万円の助成をするために、事務費を 2514万円もかけているのですから、何のための事業だかわかりません。
助成件数が伸び悩んだため、事務費が削減できなかったということだけではなく、当初から、この制度設計は酷かったため、委員会でも複数人が指摘しています。
2024年9月に補正予算を企画総務委員会で審議した時、計画の時点で、1世帯10万円のエアコン助成をするのに63,000円も事務費をかけると委員会で説明をされていたのです。計画の時点で、63000円もかけるのであれば、重層的支援として、高齢者の生活実態調査等の訪問を兼ねるなど意義づけをすべきではないですか。
計画の時から、事務費が問題であることは指摘してきましたが、最終的に1件50万円もの事務費、11~3月のコールセンターへの支出が主というのは理解に苦しみます。企業への事務費にこんなにもゆるくて、なぜ、対象世帯は、こんなにも絞り込まれなければならないのでしょうか。2度とこのようなことがないよう、改めていただきたいです。
・子ども食堂食材提供事業について
こちらの事業についても、農作物等購入費が31万円に対して、88万円もの配送費がかかっています。板橋区で作った野菜を子どもたちに食べてもらいたいという趣旨は賛同しますが、こちらも事業スキームに問題ありです。以前から指摘していますが、改善ができないようであれば、一旦中止し、再度、事業モデルを作り直していただくよう要望します。
・病児保育におけるお迎えサービス
この事業は、過去、総括質問でも指摘しましたが、利用者が令和5年の5人を除いて、令和2年から6年度まで、利用者は毎年0人です。
5年間で5人しか利用していない事業に、5100万円支出するのは異常ではありませんか。子育てしやすい街と評価されるために、設置しておく事業なのですか?利用されていないサービスで評価されるより、年間1200万円を使って、違ったものを生み出した方が良いのではないでしょうか。改善を求めます。
・生活保護家庭のアルバイト代について
先日の総括質問で、いわい議員から生活保護家庭のアルバイト代についての収入認定について、改善が要望されました。私自身も、強く共感します。
高校生年代に当たる15歳、16歳、17歳のアルバイト代が、生活保護世帯であると世帯収入として収入認定されてしまうことの理不尽さについて、私も過去、平成30年から委員会や一般質問等で質問してきました。
30年度決算で初めて、高校生のアルバイト代がいくら収入認定されているのか、調査し明らかにしてくださいましたが、令和元年は3392万円で、その後、1800万円〜2000万円あたりを推移し、令和6年度は775万円と減ってきていますが令和7年度はまた増えそうです。
私は高校生のアルバイト代の収入認定を0にする目標を板橋区に持っていただきたいと考えています。なぜなら、生活保護家庭に生まれたということで、自分自身で頑張って稼いだアルバイト代を収入認定されてしまうのはおかしいからです。
部活や、学業や、将来の進路など、認定除外してもらえる部分もありますが、現状の取り扱いは限定的です。貧困の連鎖解消を目指すなら、すぐに全額自由に使えなくても、せめて、子どもが自分自身で稼いだお金は、自分のために、長期にわたり貯蓄をできるようにすることが必要です。将来進学するかしないか、何を目指すか。見えていない高校生は多いと思います。何かチャレンジしたいことができたときに向けて、貯蓄していく権利はあるはずです。
高校生の稼働収入については、法律的には家族の世帯収入という形で認定されるというのが大原則ということですが、これは行政による子どもへの虐待ではないでしょうか。生まれながらにして不公平となっているこの制度の改善を区として国に強く要望していってほしいと考えます。
・保育園における延長保育、課外活動について
働き方改革等により、延長保育を利用する保護者が減っています。
延長保育の利用者数は、令和元年に区立保育園61188人、私立保育園216740人だったのが、令和6年度は、区立保育園29018人、私立保育園で131827人となり、区立保育園で53%減少、私立保育園で39%減少しています。
延長保育を日々使う方、たまに使う方、全く使わない方と保護者はグループ化できると思います。
延長保育の利用者が減る中で、利用者が少ないので、延長保育の利用を躊躇している例も聞きます。延長保育の利用者が少なくなっている現状に即して、延長保育の園を絞ることは、延長を日々もしくはたまに使う親子にとっても、「自分の子だけが」という思いをすることがなくありがたいのではないでしょうか。
共働きフルタイム世帯やひとり親で働いている世帯など、延長を使うことが多い家庭は、病児保育の必要性も高まります。いつもの保育園の中で病児・病後児保育を行えれば、子どもも親も安心ですし、子育て世帯は望んでいると思います。また、体験の格差も広がらないよう、ぜひ、保育園においても、課外活動や習い事など、希望すればできるように、検討を進めていただきたいと思います。
・保育園での午睡(お昼寝)について
保育園での午睡が3歳、4歳、5歳の途中まで、原則として実施されていることは子どもの成長に即していないと考えます。
幼稚園の場合、午睡はありません。幼稚園の子が、午睡は必要なく、保育園の子は必要であるということはあり得ません。もちろん、お昼寝がしたい子や休息が必要な子についてまで午睡を無くす必要はないですが、保育士さんたちの休憩時間や事務時間等の問題で、子どもたちを寝かせないと仕事にならないということは避けるべきで、人員配置を手厚くすることを求めます。
・小中学生の居場所について
児童館は乳幼児向けになったものの、午後の時間はお昼寝もあり利用者が少ないこと、夕方のホールの利用者数もカウントしたところ多いとは言えないこと、また、使われていない部屋も多いことが児童館を全館回った児童館調査で見えてきたことです。また、あいキッズの利用者が、ほとんどが小学生の低学年のみであることや、i-youthは、近隣の中学校の2校のみが利用しているということはも、関連して浮かび上がってきた調査結果でした。
それ以来、児童館のあり方や中学生の居場所の設置など、前に進みそうな雰囲気もありましたが、もう少しスピードアップして、子どもたちの環境整備をできないでしょうか。皆さんの1年と、こどもの1年は、全く感じ方が違います。検討している間に、どんどん子どもたちは大きくなっていきます。板橋区全体で、こどもの遊び場・居場所計画を作っていただき、早急に進めていただきたいです。
特に猛暑の中、こどもたちはどこにいけばいいのか。児童館でもう一度、小学生がホールで卓球など、身体を動かせる遊びを導入してください。あいキッズの枠ででもできるなら、夏休みには、もう少し高学年の子たちも自由に、体育館や校庭で遊べる設計にするなど検討を進めてください。
・こどもの池について
板橋区は、子どもの池を噴水施設等に転換していこうとしています。噴水施設については、水たまりがある程度できれば、乳幼児は楽しめるため良い側面もありますが、大きくなってくると、噴水や水深の浅いこどもの池には来なくなります。
水深のあるこどもの池は貴重な遊び場であるため、区内に水遊びが思いっきりできる水深のある遊び場を計画的に残していただきたいです。
財政調整基金がこんなにも積み上がっているので、できるはずです。小学生の夏休みは昔はプールがありましたが、今はありません。区長の答弁で競技用のプールと遊びが中心の子どもの池を並列するのは、とありましたが、水深のあるプール=競技用ではありません。浮き輪を使ったり、ボールで遊んだり、小学生でも遊びが中心のプールもあり、他区でも整備されているところがあり、検討を求めます。
・地域活動への予算化について
コールセンターに2500万円、配送に88万円、使われていないお迎えサービスに1200万円。極め付けは財政調整基金が368億円。
こういった状況の中で、地域活動への予算化については、いつも大変厳しく予算化されているように感じます。こども食堂や多世代食堂、介護予防の通いの場等の常設化への予算はつかず、ボランティア頼み。プレーパークは重要だが予算はつけない。いっぴん会の活動との連携も積極的とは言えない状況。総合事業の訪問Bも、月2万円の予算なのに、団体の実態に合わせた使い方できない。
コールセンターに大盤振る舞いするよりも、地域活動に投資した方が、10年後の未来は明るいと考えます。再考を願います。
・まちづくりについてまちづくり計画について
現在板橋区では、高島平地域、大山駅周辺地区、板橋駅西口周辺地区などで再開発事業が進められています。何度も申し上げておりますが、どこに行っても同じ街にならないよう、タワマンや駅前広場ありきではなく、その街らしさを活かし、住民との対話によるボトムアップでのまちづくりを進めていただきたいと考えます。
次に、特別会計についてです。
・国民健康保険事業特別会計について
国民健康保険の保険料は目を疑うほど高額で、根本的な見直しが必要と考えますが、決算に反対するものではありません。子育て世帯の保険料軽減については、ぜひ、前に進めていただきたく、要望します。
・東武東上線連続立体化事業について
立体化やそれに伴う広場については反対するものではありません。しかし、特に26号線を通すことによる、商店街の分断や歴史あるアーケードを壊すことについては、大山らしさを失うことになると考えるため、計画を見直すよう要望します。
以上で、いたばし未来会議の討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。
#板橋区議会
#令和6年度決算
#いたばし未来会議
#無所属
#討論